食後のだるさ、実は血糖値スパイクが原因かも?
食事の後、なんだかボーッとしたり眠くなったりしませんか?
それ、もしかすると血糖値スパイクのサインかもしれません。
健康診断で「血糖値がちょっと高め」と言われた経験のある方や、家族の健康が気になる方へ。
今回は、私自身が実践している食事での血糖値スパイク対策を3つご紹介します。
どれも今日から始められる簡単な方法ばかりです。
※この記事は個人の経験に基づいたセルフケア情報です。医療的な判断や治療については、必ず医療機関にご相談ください。
血糖値スパイクって何?なぜ起こるの?

血糖値スパイクとは
血糖値スパイクとは、食事の後に血糖値が急激に上昇する現象のことです。
通常、食事をすると血糖値は緩やかに上がりますが、スパイクが起こると急激に跳ね上がってしまいます。
健常者では空腹時血糖値は70-110 mg / dL程度といわれていますが、食後の急激な上昇は体に様々な影響を与える可能性があります。
こんな症状に心当たりは?
血糖値スパイクが起こると、以下のような症状を感じることがあります。
- 食後の強い眠気
- だるさやふらつき
- 集中力の低下
- イライラしやすくなる
- お腹が空いているのに食欲がない
これらの症状、「食べ過ぎたから」と思っていませんでしたか?
実は血糖値の急激な変動が関係している可能性があるんです。
なぜ血糖値スパイクが起こるの?
主な原因は以下の通り↓
炭水化物の一気食べ
ご飯やパン、麺類などを最初に食べると、糖質が一気に体に入り込みます。
特に空腹時にいきなり糖質を摂取すると、血糖値が急上昇しやすくなります。
早食いの習慣
忙しい現代人に多い早食いは、血糖値を急上昇させる大きな要因の一つです。
短時間で大量の食べ物が体に入ると、血糖値のコントロールが追いつかなくなってしまいます。
食物繊維不足
野菜不足の食事は、糖質の吸収を緩やかにする食物繊維が足りません。
厚生労働省策定の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、一日あたりの「目標量」は、18~64歳で男性21g以上、女性18g以上となっていますが、多くの方がこの目標量に達していないのが現状です。
【実践術1】食べる順番を変えるだけ!ベジファースト戦略

野菜→タンパク質→炭水化物の順番で食べる
この方法、実際に試してみると本当に違いを感じられます。
食後の眠気やだるさが明らかに軽減されたんです。
やり方はとってもシンプル。いつもの食事の食べる順番を変えるだけです。
具体的な実践方法
1. まずは野菜から(5-10分かけて)
- サラダ、煮物、お浸しなど
- よく噛んでゆっくり食べる
- 満腹感も得られて一石二鳥
最初は「野菜だけ?」と物足りなく感じるかもしれませんが、しっかり噛むことで満足感が得られます。
2. 次にタンパク質(肉・魚・卵・豆腐など)
- メインのおかずをしっかり味わう
- ここでも急がずゆっくりと
- タンパク質は血糖値の上昇を緩やかにしてくれます
3. 最後に炭水化物(ご飯・パン・麺類)
- この頃には満腹感も出てくる
- 自然と食べ過ぎを防げる
- いつもより少ない量でも満足できるように
外食時の工夫
外食でも応用できます。私がよく使う方法をご紹介。
定食屋さんでは
小鉢の野菜料理から手をつける。お浸しやサラダがあれば迷わずそこから。
コンビニ弁当では
野菜サラダを追加購入して最初に食べる。ちょっとした投資で大きな効果が期待できます。
ラーメン店では
もやしや海苔、メンマから食べ始める。スープを少し飲んでから麺に進むのもおすすめ。
ファミリーレストランでは
サラダバーがあれば積極的に活用。なければサイドサラダを注文。
おすすめアイテム:小さめの取り皿
野菜を少しずつ取り分けて食べるのに便利です。
100円ショップでも手軽に購入できますし、食事の順番を意識するきっかけにもなります。
見た目も上品になって、食事の時間がより楽しくなります。
【実践術2】「糖質ちょい減らし」で無理なく継続

完全に糖質を抜くのではなく「ちょい減らし」
極端な糖質制限は続きません。
私も最初は「糖質完全カット」を試しましたが、3日で挫折しました。
大切なのは「ちょっとだけ減らす」こと。
これなら無理なく続けられて、血糖値スパイクの予防にも効果的です。
具体的な減らし方
ご飯編
- いつもの8割程度に減らす
- 雑穀米や玄米に変更(食物繊維も増える)
- お茶碗を少し小さめに変更
最初は物足りなく感じるかもしれませんが、野菜やおかずを先に食べていると、案外この量で満足できるようになります。
パン編
- 全粒粉パンやライ麦パンを選ぶ
- 厚切り1枚を薄切り1.5枚に変更
- 具材(野菜やタンパク質)を増やす
パンは血糖値が上がりやすい食品ですが、選び方と食べ方を工夫すれば大丈夫。
特に具材を増やすことで、満足感もアップします。
麺類編
- 野菜たっぷりのスープを先に飲む
- 麺を少し残すか、野菜や肉を追加注文
- こんにゃく麺やしらたきを混ぜる
ラーメンやうどんが好きな方には辛いかもしれませんが、野菜をたっぷり入れることで栄養バランスも良くなります。
置き換えテクニック
カリフラワーライス
冷凍食品で手軽に購入可能。ご飯に混ぜて使うと違和感なし。
最初は半分ずつ混ぜて、慣れてきたら比率を調整してみてください。
おからパウダー
小麦粉の代替として使える。お好み焼きやハンバーグにも活用できます。
食物繊維も豊富で、血糖値対策には一石二鳥です。
こんにゃく米
普通のお米に混ぜて炊くだけ。食感もほとんど変わりません。
挫折しないためのコツ
完璧を目指さない(8割できればOK)
毎食完璧にできなくても大丈夫。続けることが一番大切です。
好きな食べ物は完全に我慢しない
月に数回は好きなものを思いっきり食べる日があってもいいんです。
週に1-2回は「自由な日」を作る
ストレスをためないことも、長続きの秘訣です。
おすすめグッズ:デジタル計量器
最初だけでも量を測ってみると、適量の感覚が身につきます。
1,000円程度で購入できて、料理の際にも重宝しますよ。
【実践術3】食事のタイミングと食べ方を工夫

ゆっくり食べる習慣を身につける
20分ルール
満腹感を感じるまで約20分かかると言われています。
最低でも15-20分はかけて食事することで、血糖値の急上昇を防ぎ、食べ過ぎも防止できます。
具体的な「ゆっくり食べ」テクニック
1. 一口30回噛む
最初は数えながらでOK。慣れると自然にできるようになります。
よく噛むことで唾液の分泌も促され、消化にも良い影響があります。
2. 箸を一度置く
一口食べたら箸を置いて、飲み物を飲む習慣を。
これだけで食事時間が自然と長くなり、ゆっくり食べられるようになります。
3. 会話を楽しむ
家族や友人との食事では、会話を挟みながら。
楽しい食事時間は、ストレス軽減にもつながります。
4. スマホやテレビを見ながら食べない
「ながら食べ」は早食いの原因になります。
食事に集中することで、満足感も高まります。
食事の間隔を意識する
朝食を抜かない
朝食を抜くと昼食時の血糖値スパイクが起こりやすくなります。
忙しい朝でも、バナナやヨーグルトなど簡単なものでも食べるようにしましょう。
間食のタイミング
- 食事の3-4時間後
- ナッツ類やヨーグルトなど血糖値を上げにくいものを
- 量は手のひらに乗る程度で十分
夕食は就寝3時間前まで
遅い夕食は血糖値が下がりきらない原因になります。
どうしても遅くなる場合は、軽めの食事を心がけましょう。
水分補給も大切
食事と一緒に水やお茶をゆっくり飲むことで、満腹感も得られ、消化もスムーズになります。
特に無糖の緑茶は、血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できると言われています。
糖分の入った飲み物は避けて、水やお茶を選ぶようにしましょう。
おすすめアイテム:タイマー
食事時間を測る習慣をつけると、自然とゆっくり食べられるようになります。
スマホのタイマー機能で十分です。
最初は15分に設定して、それより早く食べ終わらないように意識してみてください。
継続のコツと注意点

無理なく続けるために
小さな変化から始める
3つの方法を全部いきなり始めるのではなく、1つずつ取り入れていきましょう。
私は最初「食べる順番」から始めて、慣れてきたら他の方法も追加しました。
完璧を目指さない
「今日はできなかった」と落ち込まず、「明日からまた頑張ろう」の気持ちで。
7日のうち5日できれば上出来です。
家族や周りの人に協力してもらう
一人で頑張るより、家族みんなで取り組むと続けやすくなります。
「今日は野菜から食べようね」と声をかけ合うだけでも効果的です。
記録をつけてみる
食事内容や体調の変化を簡単にメモするだけでも、続ける励みになります。
スマホのメモ機能や手帳を活用してみてください。
外食が多い方へのアドバイス
コンビニを上手に活用
- サラダを追加購入
- おでんの野菜類から食べ始める
- 野菜ジュースを食事前に
ビジネスランチでの工夫
- 定食を選ぶ時は野菜が多めのものを
- 会話をしながらゆっくり食べる
- デザートは控えめに

こんな時は専門家に相談を
生活習慣の改善を続けても以下のような場合は、医療機関への相談をおすすめします:
- 数値の改善が見られない場合
- 体調に不安を感じる時
- より詳しい食事指導を受けたい場合
- 家族歴に糖尿病がある場合
生活習慣の改善は、小さな積み重ねが大きな変化につながります。
無理をせず、自分のペースで続けることが何より大切です。
今日から始める血糖値スパイク対策

血糖値スパイクは、食事の工夫で改善できる可能性があります。
今回ご紹介した3つの方法:
- 食べる順番を変える(ベジファースト)
- 糖質をちょい減らし
- ゆっくり食べる習慣
どれも特別な道具や費用は必要ありません。
明日の食事から、まずは1つだけでも試してみませんか?
私自身、これらの方法を続けることで、食後の体調が明らかに改善されました。
完璧を目指さず、できることから少しずつ。
小さな変化の積み重ねが、きっと健康な毎日につながるはずです。
「少しの意識で、もっと健康に。」
※この記事の内容は個人の経験に基づく情報提供です。健康状態に不安がある場合や、より詳しい指導をお求めの場合は、必ず医療機関にご相談ください。
参考情報
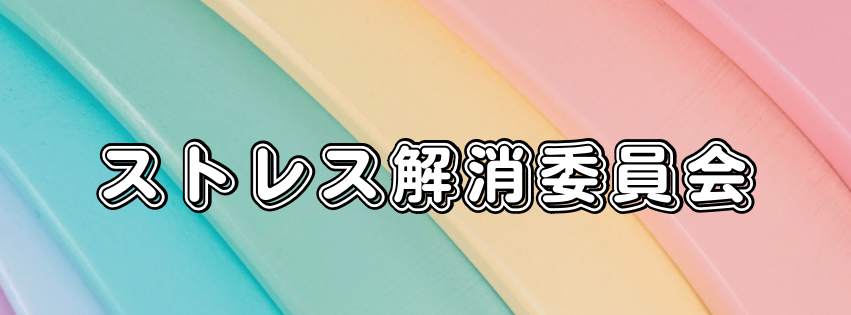





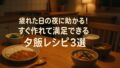
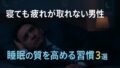
コメント